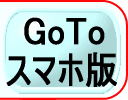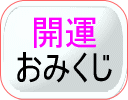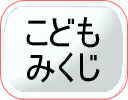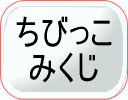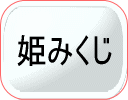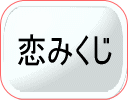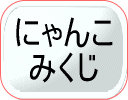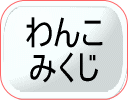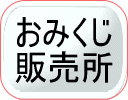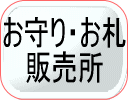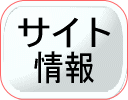|
おみくじを引くと、和歌が添えられていますが、この「おみくじに付いてくる和歌」、あるいは「おみくじに付ける和歌」とは一体何なのでしょうか。このように「おみくじの和歌」について疑問を持つ人が多いです。 |
|
一般に神社のおみくじでは和歌が添えられるのが普通ですが、明治神宮などの神社では御製や御歌が添えられています。また、寺院のおみくじでは漢詩が添えられていることもあります。寺院で漢詩が添えられるのは、おみくじのルーツである「元三大師」が僧侶だったことに由来しています。 |
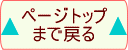
|
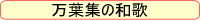
|
◆ おみくじ占い館で利用している万葉集の和歌。 |
| おみくじの和歌 (万葉集) | |||
|---|---|---|---|
|
番号 |
作者 |
和歌 |
訳文 |
|
001 |
額田王 |
熟田津に 船乗りせむと 月待てば |
|
|
002 |
中皇命 |
我が背子は 仮廬作らす 草なくは |
|
|
003 |
額田王 |
あかねさす 紫野行き 標野行き |
|
|
004 |
大海人皇子 |
紫草の にほへる妹を 憎くあらば |
|
|
005 |
天武天皇 |
よき人の よしとよく見て よしと言ひし |
|
|
006 |
持統天皇 |
春過ぎて 夏来るらし 白袴の |
|
|
007 |
高市黒人 |
ささなみの 国つ御神の 心さびて |
|
|
008 |
柿本人麻呂 |
嗚呼見の浦に 舟乗りすらむ をとめらが |
|
|
009 |
坂門人足 |
巨勢山の つらつら椿 つらつらに |
|
|
010 |
高市黒人 |
何処にか 船泊てすらむ 安礼の崎 |
|
|
011 |
山上憶良 |
いざ子ども 早く日本(やまと)へ 大伴の |
|
|
012 |
志貴皇子 |
葦べ行く 鴨の羽がひに 霜降りて |
|
|
013 |
天武天皇 |
わが里に 大雪降れり 大原の |
|
|
014 |
藤原婦人 |
わが岡の おかみに言ひて 落らしめし |
|
|
015 |
大伯皇女 |
わが背子を 大和へ遣ると さ夜ふけて |
|
|
016 |
大津皇子 |
大船の 津守が占に 告らむとは |
|
|
017 |
弓削皇子 |
古に 恋ふる鳥かも 弓絃葉の |
|
|
018 |
但馬皇女 |
人言を 繁み言痛み 己が世に |
|
|
019 |
柿本人麻呂 |
小竹の葉は み山もさやに 乱げども |
|
|
020 |
有馬皇子 |
磐代の 浜松が枝を 引き結び |
|
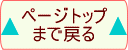
|
|
番号 |
作者 |
和歌 |
訳文 |
|---|---|---|---|
|
021 |
有馬皇子 |
家にあれば 笥に盛る飯を 草枕 |
|
|
022 |
高市皇子 |
山振の 立ち儀ひたる 山清水 |
|
|
023 |
柿本人麻呂 |
秋山の 黄葉を茂み 迷ひぬる |
|
|
024 |
柿本人麻呂 |
鴨山の 岩根し枕ける われをかも |
|
|
025 |
柿本人麻呂 |
大君は 神にし座せば 天雲の |
|
|
026 |
柿本人麻呂 |
珠藻刈る 敏馬を過ぎて 夏草の |
|
|
027 |
柿本人麻呂 |
もののふの 八十宇治川の 網代木に |
|
|
028 |
長奥麻呂 |
苦しくも 降り来る雨か 神の崎 |
|
|
029 |
柿本人麻呂 |
淡海の海 夕波千鳥 汝が鳴けば |
|
|
030 |
高市黒人 |
旅にして 物恋しきに 山下の |
|
|
031 |
高市黒人 |
四極山 うち越え見れば 笠縫の |
|
|
032 |
石川少郎 |
志賀の海人は 藻刈り塩焼き 暇なみ |
|
|
033 |
石上卿 |
ここにして 家やもいづち 白雲の |
|
|
034 |
山部赤人 |
田子の浦ゆ うち出でて見れば 真白にそ |
|
|
035 |
小野老 |
あをによし 寧楽の京師は 咲く花の |
|
|
036 |
大伴旅人 |
わが盛 また変若めやも ほとほとに |
|
|
037 |
沙弥満誓 |
鳥総立て 足柄山に 船木伐り |
|
|
038 |
額田王 |
君待つと わが恋ひをれば わが屋戸の |
|
|
039 |
阿倍女郎 |
我が背子が 着せる衣の 針目落ちず |
|
|
040 |
大伴坂上朗女 |
来むといふも 来ぬ時あるを 来じといふを |
|
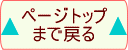
|
|
番号 |
作者 |
和歌 |
訳文 |
|---|---|---|---|
|
041 |
笠女郎 |
君に恋ひ 甚も術なみ 平山の |
|
|
042 |
笠女郎 |
相思はぬ 人を思ふは 大寺の |
|
|
043 |
紀女郎 |
今は吾は 侘びそしにける 気の緒に |
|
|
044 |
大伴坂上郎女 |
恋ひ恋ひて 逢へる時だに 愛しき |
|
|
045 |
山上憶良 |
悔しかも かく知らませば あをによし |
|
|
046 |
山上憶良 |
銀も 金も玉も 何せむに |
|
|
047 |
大伴旅人 |
わが園に 梅の花散る ひさかたの |
|
|
048 |
山部赤人 |
若の浦に 潮満ち来れば 潟をなみ |
|
|
049 |
山部赤人 |
み吉野の 象山の際の 木末には |
|
|
050 |
山上憶良 |
士やも 空しくあるべき 万代に |
|
|
051 |
石上乙麻呂 |
大崎の 神の小浜は 狭けども |
|
|
052 |
柿本人麻呂歌集 |
あしひきの 山川の瀬の 響るなへに |
|
|
053 |
作者未詳 |
幸はひの いかなる人か 黒髪の |
|
|
054 |
志貴皇子 |
石ばしる 垂水の上の さ蕨の |
|
|
055 |
山部赤人 |
春の野に すみれ摘みにと 来しわれそ |
|
|
056 |
山部赤人 |
明日よりは 春菜採まむと 標めし野に |
|
|
057 |
厚見王 |
蝦鳴く 甘奈備川に 影見えて |
|
|
058 |
山部赤人 |
恋しけば 形見にせむと わが屋戸に |
|
|
059 |
大伴家持 |
夏山の 木末の繁に 霍公鳥 |
|
|
060 |
岡本天皇 |
夕されば 小倉の山に 鳴く鹿は |
|
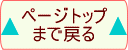
|
|
番号 |
作者 |
和歌 |
訳文 |
|---|---|---|---|
|
061 |
山上憶良 |
秋の野に 咲きたる花を 指折り |
|
|
062 |
聖武天皇 |
秋の田の 穂田を雁がね 暗けくに |
|
|
063 |
湯原王 |
夕月夜 心もしのに 白露の |
|
|
064 |
大伴書持 |
あしびきの 山の黄葉 今夜もか |
|
|
065 |
高橋虫麻呂 |
筑波嶺の 裾廻の田井に 秋田刈る |
|
|
066 |
作者未詳 |
能登川の 水底さへに 照るまでに |
|
|
067 |
作者未詳 |
真葛原 なびく秋風 吹くごとに |
|
|
068 |
作者未詳 |
高松の この峯も狭に 笠立てて |
|
|
069 |
人麻呂歌集 |
あしびきの 山道も知らず 白橿の |
|
|
070 |
柿本人麻呂歌集 |
高麗錦 紐解き開けむ 夕戸の |
|
|
071 |
作者未詳 |
朝寝髪 吾れは梳らじ うるはしき |
|
|
072 |
作者未詳 |
紅の 裾引く道を 中に置きて |
|
|
073 |
東歌 |
信濃なる 須賀の荒野に ほととぎす |
|
|
074 |
東歌 |
足柄の 箱根の山に 粟蒔きて |
|
|
075 |
東歌 |
信濃道は 今の墾道 刈株に |
|
|
076 |
東歌 |
多麻川に 曝す手作り さらさらに |
|
|
077 |
東歌 |
鳰鳥の 葛飾早稲を 饗すとも |
|
|
078 |
東歌上野国歌 |
吾が恋は まさかもかなし 草枕 |
|
|
079 |
東歌 |
稲春けば 皹る我が手を 今宵もか |
|
|
080 |
東歌 |
うべ子なは 吾に恋ふなも 立と月の |
|
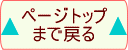
|
|
番号 |
作者 |
和歌 |
訳文 |
|---|---|---|---|
|
081 |
東歌 |
柵越しに 麦食む小馬の はつはつに |
|
|
082 |
遣新羅使 |
我が故に 妹嘆くらし 風早の |
|
|
083 |
狭野弟上娘子 |
君が行く 道の長手を 繰り畳ね |
|
|
084 |
忌部首 |
枳の 棘原刈り除け、倉立てむ |
|
|
085 |
橘諸兄 |
降る雪の 白髪までに 大君に |
|
|
086 |
大伴家持 |
かからむと かねて知りせば 越の海の |
|
|
087 |
大伴家持 |
立山の 雪し消らしも 延槻の |
|
|
088 |
作者未詳 |
安積香山 影さえ見ゆる 山の井の |
|
|
089 |
大伴家持 |
春の園 紅にほふ 桃の花 |
|
|
090 |
大伴家持 |
春の野に 霞たなびき うら悲し |
|
|
091 |
大伴家持 |
うらうらに 照れる春日に 雲雀あがり |
|
|
092 |
丈部稲麻呂 |
父母が 頭かき撫で 幸くあれて |
|
|
093 |
大舎人部千文 |
霰降り 鹿島の神を 祈りつつ |
|
|
094 |
大伴部広成 |
ふたほがみ 悪しけ人なり あた病 |
|
|
095 |
他田部子磐前 |
ひなくもり 碓氷の坂を 越えしだに |
|
|
096 |
宇遅部黒女 |
赤駒を 山野にはがし 捕りかにて |
|
|
097 |
物部刀自売 |
色深く 背なが衣は 染めましを |
|
|
098 |
大原桜井 |
佐保川に 凍り渡れる 薄氷の |
|
|
099 |
大伴家持 |
あしひきの 八峰の椿 つらつらに |
|
|
100 |
大伴家持 |
新しき 年の始の 初春の |
|