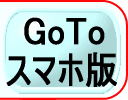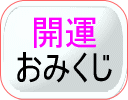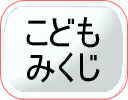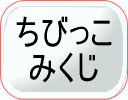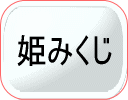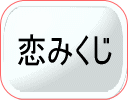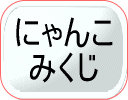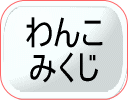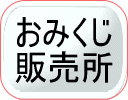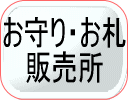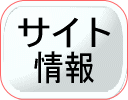|
神社などでおみくじを引くと、普通、和歌が添えられていますが、本来はこの和歌の内容から運勢を占うという、基本的な考え方、習わしがあるからです。 |
|
一般に神社のおみくじでは和歌が添えられるのが普通ですが、明治神宮などの神社では御製や御歌が添えられています。古来より日本の神々は和歌を詠むとされ、神からのごお告げ・ご託宣も和歌の形で示されることが多かったからとされます。
『おみくじ』 『開運おみくじ』
当サイトには、主流で普通の『開運おみくじ』の他に、『こどもみくじ』や『ちびっこみくじ』などがありますが、これらのおみくじは、子供用のおみくじということもあって、和歌ではなく、〔いろはがるた〕を用いています。
・江戸いろはがるた
大坂いろはがるたは、いわゆる江戸時代の大坂で流行ったものですので、「大阪」ではなく「大坂」の文字が使われています。(現在の「大阪」は江戸時代には「大坂」と書かれていました。) |
|
〔いろはがるた〕は〔いろはかるた〕とも呼ばれる短歌のカルタです。
「色は匂へど 散りぬるを
「いろはにおえど ちりぬるを
いろはがるたには、どのようなカルタがあるのか、下記にいろは歌の順番で、〔江戸〕〔京都〕〔大坂〕のそれぞれについて示します。ここではそれぞれの句の意味についても紹介しています。 |
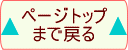
|
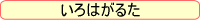
|
◆ おみくじ占い館で利用しているいろはがるた。 |
| おみくじのいろはかるた (江戸いろはかるた・京都いろはかるた・大坂いろはかるた) | |||
|---|---|---|---|
|
番号 |
江戸 |
京都 |
大坂 |
|
01:い |
犬も歩けば棒に当たる
何かしようとすると思わぬ災難に遭う。また、じっとしていないで色々やってみると思わぬ幸運に出会えるということ。 |
一寸先は闇
ほんの少し先のことも予測できはしないということ。 |
一を聞いて十を知る
事の一部を聴いただけで全部を理解するということ。転じて、賢明で利口な人や察しが良いことのたとえ。 |
|
02:ろ |
論より証拠 口だけで議論を重ねるよりも、証拠を出した方が物事は明確になるということ。 |
論語読みの論語知らず
表面上の言葉だけは理解できても、それを実行に移せないことのたとえ。そのような人をあざける言葉。 |
論語読みの論語知らず
表面上の言葉だけは理解できても、それを実行に移せないことのたとえ。そのような人をあざける言葉。 |
|
03:は |
花より団子
花を愛でるような風流よりも団子という実益を選ぶこと。外観よりも実質を重んじることのたとえ。また、風流を解さない人を批判するときの言葉。 |
針の穴から天を覗く
自分の狭い見識で、大きな事柄について論じたり、勝手な判断を下すことのたとえ。 |
花より団子
花を愛でるような風流よりも団子という実益を選ぶこと。外観よりも実質を重んじることのたとえ。また、風流を解さない人を批判するときの言葉。 |
|
04:に |
憎まれっ子世に憚る
人から憎まれるような者ほど、逆に世間では幅をきかせるものであるということ。 |
二階から目薬
二階から階段下の人に目薬をさすように、物事が思うようにいかず、もどかしいさま。 また、回りくどくて効果が得られないことのたとえ。 |
憎まれっ子頭堅し
他人に憎まれるような腕白な子供は、概して健康で丈夫な子であることをいう。 |
|
05:ほ |
骨折り損のくたびれ儲け
苦労するばかりで全く利益の伴わず、疲れだけが残ること。無駄な努力。 |
仏の顔も三度
いかに温和で慈悲深い人でも、無礼をたびたび加えられればついには怒り出すとのたとえ。 仏の顔も三度撫なづれば腹立つる。 |
惚れたが因果
惚れたのが運の尽き。好きになったのだから苦労するのも仕方がない。惚れたのが運の尽きということ。 |
|
06:へ |
屁をひって尻窄める
失敗した後で、慌てて隠したり、取り繕うこと。過ちをしでかして、あわててごまかそうとすることのたとえ。 |
下手の長談義
話が下手な人ほど、だらだらと長話をするということ。 |
下手の長談義
話が下手な人ほど、だらだらと長話をするということ。 |
|
07:と |
年寄りの冷や水
老人が冷や水を浴びるような、年齢にふさわしくない危険なまねや、出すぎた振る舞いをすること。 |
豆腐に鎹(かすがい)
豆腐に鎹を打ちこんでも豆腐が崩れるだけで役に立たないことから、手ごたえがないこと、効き目がないことのたとえ。 |
遠くの一家(いっけ)より近くの隣
いざという時には遠くにいたり疎略にしている親類より、近くにいて親しくしている他人の方が頼りになる。遠くの親類より近くの他人。 |
|
08:ち |
塵も積もれば山となる
塵のように小さなものでも、積もり積もれば山のように大きくなることのたとえ。小いさな事でも疎かにしてはいけないという戒め。 |
地獄の沙汰も金次第
地獄の閻魔さまの裁きでさえも、金の力で自由になるというほどだから、この世では金さえあれば何でもできるというたとえ。 |
地獄の沙汰も金次第
地獄の閻魔さまの裁きでさえも、金の力で自由になるというほどだから、この世では金さえあれば何でもできるというたとえ。 |
|
09:り |
律義者の子だくさん
義理がたく実直な人は浮気などせず夫婦仲もよいので、子供がたくさんできるということ。 |
綸言(りんげん)汗のごとし
皇帝が一旦発した言葉(綸言)は、体から出た汗のように再び体内には戻らないのと同じように、取り消したり訂正することができないということ。 |
綸言(りんげん)汗のごとし
皇帝が一旦発した言葉(綸言)は、体から出た汗のように再び体内には戻らないのと同じように、取り消したり訂正することができないということ。 |
|
10:ぬ |
盗人(ぬすびと)の昼寝
盗人が昼寝するのは何の意味もなさそうだが夜、盗みをするために体を休めているということから、何の目的もなさそうに見える行為も、それ相応の思惑や理由があるものだというたとえ。 |
糠(ぬか)に釘
柔らかい糠に釘を打ち込んでも、糠に埋もれるだけで役に立たないことから、手応えがない、効き目がないことのたとえ。 |
盗人(ぬすびと)の昼寝
盗人が昼寝するのは何の意味もなさそうだが夜、盗みをするために体を休めているということから、何の目的もなさそうに見える行為も、それ相応の思惑や理由があるものだというたとえ。 |
|
11:る |
瑠璃(るり)も玻璃(はり)も照らせば光る
すぐれた素質や才能がある者は、どこにいても目立つというたとえ。また、そのような者が活躍の場を与えられたときには能力をいかんなく発揮するということ。 |
類をもって集まる
似た者同士は互いに寄り集まることのたとえ。また、善人の周りには善人が集まり、悪人の周りには悪人が集まるということのたとえ。 |
類をもって集まる
似た者同士は互いに寄り集まることのたとえ。また、善人の周りには善人が集まり、悪人の周りには悪人が集まるということのたとえ。 |
|
12:を |
老いては子に従え
年をとったら出しゃばったり我を張ったりず、何事も子に任せて、これに従っていく方がいいということ。 |
鬼も十八
鬼でも年ごろになれば少しは美しく見えだろうということから、器量が悪くても年ごろになれば少しは娘らしい魅力が出てくるということのたとえ。 |
鬼の女房に鬼神
鬼のように冷酷無比な夫には、それと同じような女房がいるということ。似たもの同士のたとえ。 |
|
13:わ |
破(わ)れ鍋に綴(と)じ蓋
壊れた鍋にもそれに合う蓋があることから、どんな人にもふさわしい伴侶がいるものだというたとえ。また、何においても似通った程度の者同士がよいというたとえ。 |
笑う門には福来る
いつもにこやかに笑っている人の家には、自然と幸福がやって来るということ。 |
若い時は二度ない
人生では若いときは二度とないのだから、若いうちに何でも思い切ってやってみるのがよいということ。 |
|
14:か |
かったいの瘡(かさ)うらみ
大差ないものを見てうらやむこと。また、ぐちをこぼすことともいう。 |
蛙の面に水
蛙の顔に水をかけても平気なように、どんな目にあわされても何も気にせず、平気でいることのたとえ。 |
陰裏(かげうら)の豆もはじけ時
日陰に植えた豆も時期がくれば成熟することから、どんな娘でも年頃になると色気づくことのたとえ。 |
|
15:よ |
葦(よし)の髄(ずい)から天井覗く
細い葦(よし)の茎の穴を透かして天井を見て、天井の全部を見たような気になることから、自分だけの狭い見識で、大きな問題を論じたり、判断することのたとえ。 |
夜目遠目(とめとおめ)笠のうち
夜見るとき、遠くから見るとき、笠に隠れた顔の一部をのぞいて見るときは、はっきり見えないので実際より美しく見えるものであるということ。 |
よこ槌で庭を掃く
わらを打つとき使う横槌で庭を掃く様子から、急な来客に慌てる様。急な来客に慌てながらも手厚くもてなそうとすること。 |
|
16:た |
旅は道連れ世は情け
旅をするときに道連れがいると心強いように、世の中を渡っていくには人情をもって仲良くやっていくことが大切だということ。 |
立て板に水
立てた井谷水をかけると、よどみなく流れることから、弁舌が達者で、すらすらと流れるようにしゃべること。 |
大食(だいじき)上戸の餅食らい
大食いしたうえ大酒を飲み、さらに餅までも食べること。 |
|
17:れ |
良薬(れうやく)は口に苦し
良い薬ほど苦いが病気を治すには効き目があることから、自分のためになるような忠言は、素直に聞きづらいものだというたとえ。 |
連木(れんぎ)で腹切る
連木とはすりこぎのことで、すりこ木で腹を切ることはできないことから、不可能なことのたとえ。 |
連木(れんぎ)で腹切る
連木とはすりこぎのことで、すりこ木で腹を切ることはできないことから、不可能なことのたとえ。 |
|
18:そ |
総領(そうりょう)の甚六
総領とは長男の事で、長男は大事に育てられるので、弟や妹に比べておっとりしており、世間知らずが多いということのたとえ。 |
袖すり合うも他生の縁
知らない人とすれ違いざまに袖が触れ合うようなちょっとしたことでも、前世からの因縁によって起きるということ。 |
袖すり合うも他生の縁
知らない人とすれ違いざまに袖が触れ合うようなちょっとしたことでも、前世からの因縁によって起きるということ。 |
|
19:つ |
月とすっぽん
月とすっぽんとは、比較にならないほど二つのものの違いが大きいこと。 |
月夜に釜を抜かれる
月明りがある明るい夜に釜を盗まれることから、とても油断していることのたとえ。 |
爪に火をともす
ろうそくの代りに爪に火を灯す様子から、貧しい暮らしぶりや極端な倹約ぶり、非常にケチなことのたとえ。 |
|
20:ね |
念には念を入れよ
用心の上に、さらに用心を重ねよということ。注意した上に、さらに注意せよということ。 |
猫に小判
猫に小判を持たせても価値が分からないことから、価値の分からない人に貴重なものを与えても何の役にも立たないことのたとえ。 |
寝耳に水
寝ている時に濁流音を聞いて驚く様子から、突然、思いがけない出来事に出くわし驚くことのたとえ。 |
|
21:な |
泣きっ面に蜂
泣いているときに、更に蜂に刺されてしまうことから、困っている状況や悲惨な状況にさらに困り事や不幸・災難が舞い込んでくることのたとえ。 |
済(な)す時の閻魔顔
他人から金品を借りるときにはニコニコしているが、返済するときには渋い顔をすることのたとえ。 |
習わぬ経は読めぬ
知識や経験のまったくない物事をやれと言われても、できるものではないということのたとえ。 |
|
22:ら |
楽あれば苦あり
人生は楽しいことばかりでなく、苦しいこともあるということ。楽しいことがあると、その後に必ず苦しいことがあるという教え。 |
来年の事を言えば鬼が笑う
明日なにが起こるか分からないのに来年のことなど分かるはずもない。未来は予測できるわけがないのだから、あれこれ言ってみても仕方がないというたとえ。 |
楽して楽知らず
苦労を知らない人には、安楽のありがたみが分からない。苦労して初めて安楽さの大切さがわかるということ。 |
|
23:む |
無理が通れば道理が引っ込む
道理に反することがまかり通る世の中なら、道理にかなった正義は行われなくなるということ。 |
昔とった杵柄
昔とった杵柄とは、若い頃に身に付けた技量や腕前のこと。 また、それが衰えないこと。 |
無芸大食
これといった特技や才能はない代わりに、食べることだけは人並みはずれていること。また、その人。 |
|
24:う |
嘘から出た実(まこと)
嘘として言っていたことが、結果として本当になってしまうこと。また、冗談で言ったことが、偶然にも真実になること。 |
氏(うじ)より育ち
家柄や身分よりも、育った環境やしつけのほうが人間の形成に強い影響を与えるということ。 |
牛を馬にする
劣ったものを捨て、すぐれたものに乗り換えること。また、自分にとって不利な方から有利な方に切り替えることのたとえ。 |
|
25:ゐ |
芋の煮えたも御存知ない
芋が煮えたのかどうかの判定もできないことから、世間知らずでおっとりした人を、馬鹿にしてあざけることば。 |
鰯の頭も信心から
鰯の頭のようなつまらないものでも、信仰すれば尊いものとなることから、信仰心の不思議さのたとえ。新興宗教などに対しての皮肉に使われることが多い。 |
炒豆(いりまめ)に花が咲く
炒った豆に花が咲くことはありえないことから、とてもありえないことが起こる様子、奇跡が起こることのたとえ。一度衰えていたものが再び勢い盛り返すこと。ありえないことが実現すること。 |
|
26:の |
喉元過ぎれば熱さを忘れる
苦しいことも過ぎてしまえば、その苦しさや恩も簡単に忘れてしまうということ。 |
鑿(のみ)と言えば槌(つち)
鑿を持ってくるように言われたら、一緒に使う槌ももってくることから、万事に気が利くことのたとえ。 |
野良の節句働き 普段怠けている者に限って、休日に働き出すものだということ。 |
|
27:お |
鬼に金棒
もともと強い者がさらに強くなるということ。 |
負うた子に教えられて浅瀬を渡る
熟達した者であっても、時には自分より経験の浅い者や年下の者に、物事を教わることもあるものだというたとえ。 |
陰陽師身の上知らず
陰陽師は他人の吉凶ばかり占っているが、自分の運命についてはわからない。他人のことはよくわかる人でも自分のことはわからないということ。 |
|
28:く |
臭いものに蓋をする
人に知られたくないことや悪事を、その場しのぎの手段で隠そうとすること。 |
臭い物に蝿がたかる
くさい者に蠅が集まるように、悪い者同士は寄り集まるものだということ。 |
果報(くゎはう)は寝て待て
幸運は人の力でどうすることもできないので、人事を尽くして後は気長に良い知らせを待つしかないということ。 |
|
29:や |
安物買いの銭失い
値段が安いものは品質が悪いので、買い得と思っても結局は修理や買い替えで高くつくということ。 |
闇夜に鉄砲
あてずっぽうにやってみること。また、当たるはずもないこと、まぐれ当たりのことをいう。 |
闇に鉄砲
目標の定まらないこと。また、目標を定めずに事をなすこと。しても意味のないことのたとえ。 |
|
30:ま |
負けるが勝ち
時と場合によっては、争わないで相手に勝ちを譲ったほうが自分にとって有利な結果になり、自分の勝ちに繋がるということ。 |
蒔かぬ種は生えぬ
原因がないのに結果が生じることはないというたとえ。また、努力もせずに良い結果を期待することなど無駄だという教え。 |
待てば甘露(かんろ)の日和あり
待っていれば、甘露が降ってくるような日和もある。あせらずにじっくりと待っていれば、やがてよい機会がめぐってくる。 |
|
31:け |
芸は身を助ける
ひとつでも秀でた芸があると、いざというとき役に立つということ。芸にすぐれていると、困窮したときにそれが生計の助けにもなるということ。 |
下駄と焼き味噌
板につけて焼いた味噌の形は、下駄に似ているが、実際は違うところから、形は似ていても、内容はまったく違っていることのたとえ。 |
下戸の建てた蔵はない
酒を飲まないからといって、そのぶん金をため蔵を建てるとは限らないことをいう。酒飲みの人の主張で、酒飲みが下戸を嘲笑していう句である。 |
|
32:ふ |
文(ふみ)はやりたし書く手は持たぬ
恋文を書きたいが、人に見せられるような文字や文章を書くことができず、代筆を頼むのも恥ずかしいと気をもむ様子をいう。 |
武士は食わねど高楊枝
武士は貧しくて食事ができなくても、あたかも食べたかのように楊枝を使って見せる。武士の清貧や体面を重んじる気風をいう。 また、やせがまんすることにもいう。 |
武士は食わねど高楊枝
武士は貧しくて食事ができなくても、あたかも食べたかのように楊枝を使って見せる。武士の清貧や体面を重んじる気風をいう。 また、やせがまんすることにもいう。 |
|
33:こ |
子は三界の首っ枷(かせ)
三界は過去、現在、未来の三つの世界の意味で、親というものは子供のことにとらわれて、一生自由を束縛されてしまうというたとえ。 |
これに懲りよ道才坊(どうさいぼう)
「これにこりて二度と繰り返すな」の意を調子よく言う言葉。 |
志は松の葉
たとえ松葉にくるむほどのわずかな物でも、贈る人の心がこもっていれば、りっぱな贈り物となることをいう。 |
|
34:え |
得手(えて)に帆を揚げ
自分が得意なことを発揮する機会が到来し、調子に乗ってことを進めること。絶好の機会が到来し、それを利用してはりきって行動を起こすこと。 |
縁と月日
縁と月日とは、縁は無理に求めず、自然に好機が訪れるのを待てということ。 |
閻魔の色事
恐ろしい閻魔が色事をすることから、似つかわしくないことのたとえ。 |
|
35:て |
亭主の好きな赤烏帽子(あかえぼうし)
烏帽子は黒塗りが普通であるが、亭主が赤い烏帽子を好めば家族はそれに同調しなければならない意から、どんなことでも、一家の主人の言うことには従わなければならないということのたとえ。 |
寺から里へ
檀家から寺へ物を贈るのが当たり前なのに、寺から檀家へ物を贈る意から、物事が逆であることのたとえ。 |
天道人殺さず
天は慈悲深くて、人を見離すことはない。 |
|
36:あ |
頭隠して尻隠さず
キジは追いかけられると草むらの中に頭を突っ込んで隠し、尾が出ているのに気づかない様子から、悪事や欠点などの一部を隠して、全部を隠したつもりでいる愚かさを嘲る言葉。 |
足元から鳥が立つ
身近なところで意外なことが突然起きること。 また、急に思い立って慌しく行動を起こすこと。 |
阿呆につける薬はない
病気ならば薬で治せるが、愚かな者は薬では治せないということ。愚かな者を教え導く方法はないことのたとえ。 |
|
37:さ |
三遍回って煙草にしょ
休むことは後にして、手落ちのないように念入りに確認をせよといういましめ。 |
竿の先に鈴
鈴を竿の先につけると、揺れてうるさくなることから、騒がしいこと、おしゃべりなことをのたとえ。 |
触らぬ神に祟りなし
その物事に関わりさえ持たなければ、災いを招くことはない。面倒なことに余計な手出しをするな、というたとえ。 |
|
38:き |
聞いて極楽見て地獄
人から聞いた話と、実際に見るのとでは大きな違いがあるということ。 |
鬼神に横道なし
鬼神に横道なしとは、鬼神は邪なこと、曲がったことはしないということ。 |
義理と褌(ふんどし)
男子は常にふんどしを付けておかねばならないように、義理を欠いてはいけないというたとえ。 |
|
39:ゆ |
油断大敵
大した事はないだろうと油断すると、思わぬ失敗を招くことから、気のゆるみを戒めたことば。 |
幽霊の浜風
幽霊が強い海の風に吹き飛ばされそうになっているさまから、元気のないさま、迫力のないさまのたとえ。 |
油断大敵
大した事はないだろうと油断すると、思わぬ失敗を招くことから、気のゆるみを戒めたことば。 |
|
40:め |
目の上の瘤(こぶ)
何かと目障りであったり、じゃまになったりするもののたとえ。目の上のたんこぶ。 |
盲(めくら)の垣覗き
やっても無駄なことのたとえ。 |
目の上の瘤(こぶ)
何かと目障りであったり、じゃまになったりするもののたとえ。目の上のたんこぶ。 |
|
41:み |
身から出た錆
身から出た錆とは、自分の犯した悪行のために、自分自身が苦しむこと。自業自得。 |
身は身で通る裸ん坊
貧富や賢い愚かの差はあっても、人はそれぞれにふさわしい暮らしをしてゆくものであり、結局は、自分を中心とする生活しかできぬものであるというたとえ。 |
蓑売りの古蓑
蓑売りの古蓑は、他人のためにばかりで、自分のことまで手が回らないこと。 |
|
42:し |
知らぬが仏
知れば腹が立ったり悩んだりするようなことでも、知らなければ平静な心でいられるということのたとえ。 また、本人だけが知らずに澄ましているさまを、あざけって言うことば。 |
しわん坊の柿の種
柿の種のような、何の役にも立たないものまで物惜しみをするひどいけちんぼう。けちんぼうをを罵っていう言葉。 |
尻(しり)食らえ観音
困ったときは観音様を念じても、困ったことが通りすぎれば恩を忘れて、あとのことをかまわないこと。 |
|
43:ゑ |
縁は異なもの味なもの
男女の縁はどこで結ばれるかわからない。とても不思議で面白いものだということ。理屈では説明できない縁があるという意。 多く思いもよらない二人が結ばれるようなときに使う。 |
縁の下の舞
縁の下の舞とは、人目につかないところで、他人を支える苦労や努力をすること。 また、そのような人。 |
縁の下の力持ち
人の目につかないところで、他人のために支える苦労や努力をすること。また、そのような人。 |
|
44:ひ |
貧乏暇なし
貧乏をしていると生活に追われて朝から晩まで働かなければならず、ほかのことをする余裕がないということ。 |
瓢箪(ひょうたん)から駒が出る
意外な所から意外な物が出てくること。ふざけて言ったことが実現することのたとえ。 |
貧相の重ね食い
貧乏で食べるものに困った者が、一度にたくさんの食べ物をたべることのたとえ。 又、いつもいいことがないのに、まとめていいことが起きてしまうことのたとえにも。 |
|
45:も |
門前の小僧習わぬ経を読む
ふだん見聞きしていると、いつのまにかそれを学び知ってしまう。 環境が人に与える影響の大きいことのたとえ。 |
餅は餅屋
何事においても、それぞれの専門家に任せるのが一番良いということのたとえ。 また、上手とは言え素人では専門家にかなわないということのたとえ。 |
桃栗三年柿八年
芽が出て実がなるまでに、桃と栗は三年、柿は八年かかるということ。また、何事も成し遂げるまでには相応の年月が必要だというたとえ。 |
|
46:せ |
急いては事を仕損じる
急いては事を仕損じるとは、何事も焦ってやると失敗しがちだから、急ぐときほど落ち着いて行動せよという戒め。 |
せんちで饅頭
せんちで饅頭とは、空腹を満たすのに場所をかまわないことのたとえ。また、人に隠れてひっそりと自分だけいい思いをすることのたとえ。 |
背戸(せと)の馬も相口(あいくち)
裏口に繋いでおくしかない暴れ馬でも、扱い方によってはおとなしくなること。手のつけられない者にも、頭の上がらない人や気の合う友人はいることのたとえ。 |
|
47:す |
粋(すい)は身を食う
遊里や花柳界などの事情に詳しくて、もてはやされ得意になっている人は、やがて深入りし身を滅ぼしてしまうという戒め。 |
雀百まで踊り忘れぬ
雀は死ぬまで飛び跳ねる癖が抜けないことから、幼い時に身につけた習慣や若い時に覚えた道楽は、いくつになっても直らないというたとえ。 |
墨に染まれば黒くなる
人は環境や交わる友によって良くも悪くも染まってしまうことのたとえ。 |
|
48:京 |
京の夢大阪の夢
夢の中では、いろいろな事を実現できたり、見たりできること、夢は不思議なものであるということ。夢では様々な願望が叶うものだということ。人それぞれ願望は違うということ。 |
京に田舎あり
賑やかなな都会の中にも、まだ開けていない田舎めいた場所や、古い習慣が残っているということ。 |
---
|